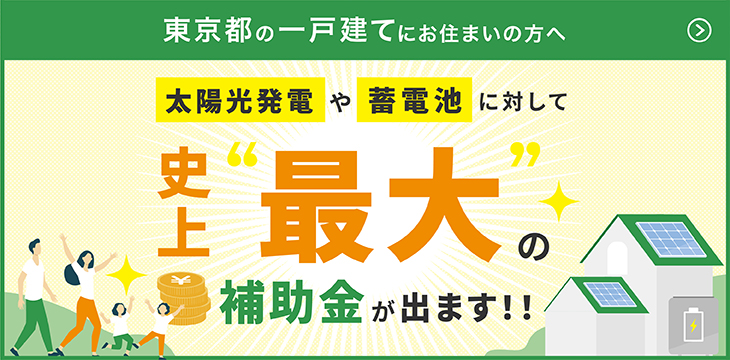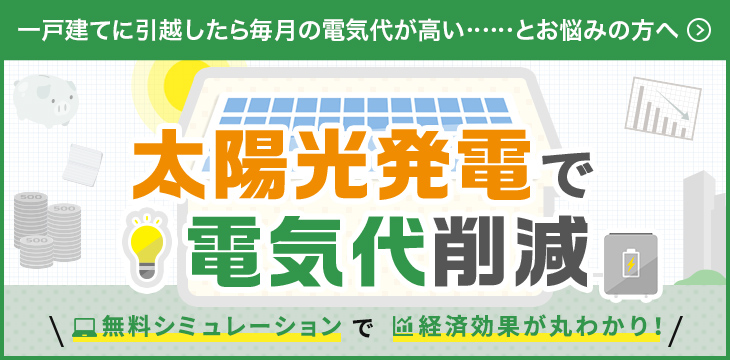「V2H」という言葉をご存じですか?「Vehicle to Home」つまり「車から家へ」を意味するこの言葉は、電気自動車に蓄えられた電力を、家庭用に有効活用する考え方のこと。エコカーの新しい可能性として注目が高まっているV2Hについて徹底解説いたします。
トピックス一覧
V2Hとは
V2Hの概要
V2H(Vehicle to Home)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に蓄えられた電力を家庭用に活用する技術です。これにより、電気自動車を移動手段としてだけではなく、家庭のエネルギー効率を高める電力供給源(走る蓄電池)としても使用することが可能です。主な特徴としては以下が挙げられます。
- 電力の双方向利用
V2Hは、家庭の電力供給と電気自動車の充電を双方向で行えるシステムです。車両からの給電を通じて、家庭のエネルギー需要を補完します。 - 太陽光発電との連携
昼間に太陽光発電システムで作られた電力を蓄え、夜間に使用することで効率的な電力活用が実現します。 - 停電時のバックアップ電源
災害や停電時にも家庭に電力を供給できるため、非常時のエネルギー対策としても注目されています。
V2Hは、電力料金の削減や環境負荷の低減といった経済的・環境的な利点があり、再生可能エネルギーやスマート家電との相性も良いことが特徴です。
V2Hの変遷
電気自動車の充電方法は次第に進化してきました。その歴史を語るうえで欠かせないのがV2Hの普及と関係が深い、EV/PHEVの充電方法の進化についてです。初期は、家庭の100Vや200Vコンセントを利用した充電が一般的でした。その後、専用の充電スタンドが普及し電気自動車に蓄えた電力を家庭用電源としても使用できるV2H対応機器が登場しました。
さらに近年では、太陽光発電の普及とともに昼間に発電した電力を蓄え、夜間に使用できる蓄電池機能を備えた製品も増えています。これにより、電気自動車を単なる移動手段としてではなく、家庭の電力を補完する重要なインフラとして活用できるようになりました。

電気の変換技術や蓄電池、充電器の性能向上、そして太陽光発電の普及……こうした時代と技術の変化に伴って単なる「充電スタンド」の枠にとどまらない高性能なV2H機器が普及。EV/PHEVをさらに賢く使用できる環境が整ってきているのです。
余談ですが、EVの充電方法やコネクターの規格にCHAdeMO(チャデモ)というものがあります。
CHAdeMOの由来には、【CHArge de MOve = 動く,進むためのチャージ】、【de = 電気】、の他に【(クルマの充電中に)お茶でも】の3つの意味が込められています。
V2Hはこんな人におすすめ
こんな人にはV2Hの導入が特におすすめです。
- 電力料金の削減をしたい方
- 電気料金の安い時間帯に充電し、家庭の電力として活用することで、電気代を大幅に節約できます。
- 災害時の備えをしたい方
- 停電時に電気自動車をバックアップ電源として使用できるため、非常時に役立ちます。
- 環境に配慮したい方
- 再生可能エネルギーである太陽光発電と組み合わせれば、環境に優しいライフスタイルを実現できます。
- 太陽光発電システムをすでに持っている方
- 太陽光発電と連携させることで、電力の効率的な活用が可能です。
- 最新技術に興味がある方
- スマート家電やIoTとも親和性が高く、技術に敏感な方には魅力的です。
V2Hの仕組み
家庭からクルマへの充電や、クルマから家庭への給電を行うV2H機器ですが、太陽光発電システムの設置の有無や、発電した電力の使い道によって選べるタイプが異なります。
非系統連系
これは、太陽光発電を未設置、または設置済みであっても、太陽光発電を「売電」にのみ利用しているケースに適しています。ただし、EV/PHEVからの給電中は電力会社からの電気を利用することができません。注意点として、電気使用量がEVからの給電量を上回ると給電は停止し、電力会社からの電力供給に切り替わる際に瞬時停電※(瞬断)が発生してしまうことが挙げられます。
※瞬時停電とは、電源からの電力供給が短い時間(数マイクロ秒から数百マイクロ秒)絶たれてしまう電源障害現象のこと。

系統連系
このタイプを使えるのは太陽光発電を既に設置済みで、発電した電気を自家消費している家庭。太陽光発電の電力、EVから給電した電力、電力会社からの電力を同時に使用することができるので安心です。

V2Hのメリット
V2Hには日常生活を豊かにするさまざまなメリットがあります。これを押さえて、導入を検討してみましょう!
1. 充電時間が短い
1つ目は、家庭用200Vの普通充電コンセントに比べて充電時間が短いこと。V2H機器を使えば、充電時間は200Vの普通充電コンセントの半分。「電気自動車に乗ろうと思ったときに十分に充電できていなかったらどうしよう……」という心配を減らすことができます。
※参考:「日産リーフの充電時間」(日産)
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/leaf/charge/charge.html
※参考:「V2Hシステム」(パナソニック)
https://sumai.panasonic.jp/v2h_chikuden/v2h_system/
2. 電気料金の節約になる
2つ目は、電気料金の節約に貢献できること。日中にクルマに乗る方の場合は、電気料金が安くなる深夜料金で充電することができます。もし日中外出しない場合は、夜間にEV/PHEVに蓄えた電気を家庭用電源として使用することで、ピークシフトにも貢献。大幅な電気代の節約が期待できます。
3. 停電時の非常用電源になる
停電時に非常用電源として機能すること。夜間に停電した際は電力会社の給電や太陽光発電の電力が利用できなくても、自動車に蓄えた電力を蓄電池代わりとして家庭で使えるので安心です。
4. 大容量の蓄電池の代わりとして活用できる
一般的な蓄電池と比べて、電気自動車の電池容量が大きいこと。一般的な家庭用蓄電池は4~12kWhの容量であるのに対し、電気自動車は10~80kWhと大容量。より長い時間、電化製品を使用することができます。また一般的な蓄電池よりも中古車として販売されている電気自動車の方が値段が安い場合もあり、実際に蓄電池代わりとして中古の電気自動車を購入される方もいらっしゃいます。
5. 補助金対象になっている
5つ目は、自治体によっては、補助金を受け取れること。EVやPHEVなどのエコカーには、自治体ごとに補助金制度を設けています。中には、車両本体だけでなくV2H機器にも補助金を支給するところもあるので、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。
6. 電気代とガソリン代の節約
EVやPHEVの利用により、ガソリン代も大幅に節約できます。ガソリン価格が高騰する中、電気自動車は安定した低コストの電力を利用でき、さらにV2Hを活用すれば家庭の電気代も節約可能です。
V2Hの導入を検討する際のポイント
V2Hの導入を検討する際には、事前に確認しておきたいくつかの重要なポイントがあります。以下に詳しく説明します。
- 自宅の電力使用状況を把握する
- 家庭での電力使用量を確認し、導入後の効果をイメージしましょう。
- EV、PHEVの利用状況を把握する
- 通勤距離や充電頻度を考慮し、最適なシステムを選択。
- V2Hシステムの種類を知る
- 系統連系か非系統連系、どちらが適しているか調べる。
- 導入費用を知る
- 本体価格や工事費用を調査し、補助金適用後の価格も確認。
- 補助金制度を活用する
- 地域の補助金を調べ、導入コストを抑えましょう。
- 設置場所を検討する
- スペースや配線の経路を考え、実現可能性を確認。
- 信頼できる業者を選ぶ
- 評判の良い施工業者を選び、トラブルを防ぎましょう。
V2Hの価格相場について
V2H機器の価格は、【本体費用+設置工事費用+その他諸費用】で算出されます。本体費用は50~180万円、工事費用は20~40万円といずれも幅広く、自治体によっては補助金が適用され、半額程度で購入できる場合もありお住まいの地域や暮らしの状況によって様々です。ご自身の暮らしや住宅に合ったV2Hを探す際は、お住まいの自治体や信頼できる販売業者に確認することをおすすめします。
メーカーごとのV2H性能比較
日本国内では、以下のメーカーが主要なV2H機器を提供しています。
| メーカー名 | 特徴 |
|---|---|
| オムロン | マルチV2X対応、自動切替機能、高効率、幅広い製品ラインナップ、高い信頼性と耐久性。 |
| デンソー | 高い安全性と対応車種の多さが特徴。 |
| ニチコン | 業界最大クラスの蓄電容量16.6kWhを実現し、多様な環境条件にも耐える安定性。 |
| シャープ | 自動で賢く充放電し、スマートライフを実現。 |
| 三菱電機 | 電気の「つくる・貯める・使う」を効率的に行うシステム。 |
V2Hシステムの導入を検討する際は、各メーカーの特徴や自宅の電力使用状況、EVやPHEVの利用状況、設置場所などを考慮し、最適なシステムを選択することが重要です。
本当にお買い得なのか?
本当にEVってお得?と感じる方もいるでしょう。確かに初期費用は高めですが、助成制度や燃料費の節約でその分を補えます。ガソリン車よりもランニングコストが安く、税金の免税・減税も活用可能です。さらに、V2H機能で家庭電力として使えるのも大きな魅力。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
V2Hは、電気自動車の可能性を広げ、家庭のエネルギー効率を向上させる魅力的な技術です。電力料金の削減や災害時の備え、環境負荷の軽減など、多くのメリットがあります。興味のある方は、まず自宅やライフスタイルに合ったV2H機器を検討し、導入に向けた一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。気になる方はお気軽にお問い合わせください。